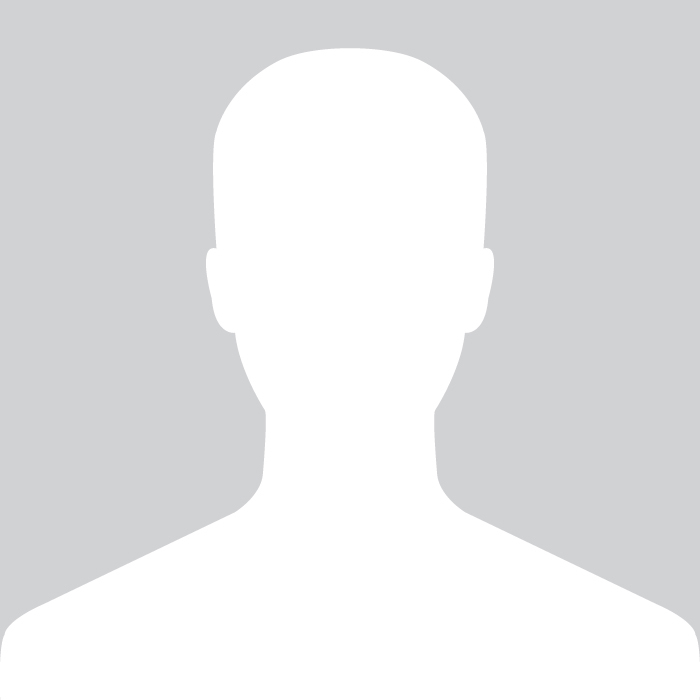SAKURUG TECHBLOG
開発したダッシュボードを運用しよう
当記事はBIツールを使ったダッシュボード開発を行う際に心がけることの続編になります。BIツールを使って開発したダッシュボードを実際に運用するにあたっての難点とその対応方法をまとめたいと思います。
ダッシュボード運用の難点
開発したダッシュボードを運用するにあたって難しい点は、
・データが更新されない
・数値の整合性に疑問が出る
の二点にあります。
データが更新されない
ダッシュボードに入るデータは、元はExcelファイル等の形でユーザ側が作成・収集したものです。ユーザが指定の場所にデータファイルをアップロードしない限りダッシュボードは始まりません。
「この日までにデータファイルを指定の形式に整えて指定の場所にアップロードしてください」と依頼しても、ユーザ側も多忙だったり忘れていたりでなかなかアップロードされないことも多いです。すると当然、ダッシュボードは更新されず、最新の情報をダッシュボード上で確認することもできなくなります。
数値の整合性に疑問が出る
ユーザ側が作成・収集したデータファイルをダッシュボードに取り込み、集計値を表示するまでには前処理というデータをクレンジングする工程が挟まります。
前処理前のデータ(生データ)を持つユーザはそのデータから集計を行い、数値を算出します。一方でダッシュボード上の数値は前処理後のデータから集計を行った数値になります。すると当然、両者の間で数値が合わないケースが生じます。
どちらが正しい数値なのか、ダッシュボード上の数値は本当に信用できるのか...といった疑問が出ることが予想されます。
対応方法
これら運用上の課題点はユーザ側とのコミュニケーションで解消するしかありません。
データ更新にあたっては周知の徹底を行い、何とかしてデータをアップロードしてもらう必要があります。しかし、ユーザ側とダッシュボード運用側の距離が離れている場合や、ユーザ側の内部でデータ収集者とダッシュボード閲覧者が離れている場合には、これは困難です。
数値の整合性に関しては、前処理後のデータを正のものとして認識を共有し、そのデータをもとに数値検証を行う必要があります。しかし当然、前処理前の生データから集計された数値もユーザ側に存在するので、どちらが正の数値なのか混乱が生じる可能性があります。
このようにダッシュボード運用には困難なことも多く、その対応方法も「こうすれば万事解決」といかないことが多いです。
ダッシュボードを開発・運用するにあたっては、アジャイル開発を基本とし、トライアル運用を随時実施するのが良いと思います。得られた知見を積み上げながら柔軟に推進していくしかないというのが実情だと思います。
▼カジュアル面談実施中!
カジュアル面談では、会社の雰囲気や仕事内容についてざっくばらんにお話ししています。
履歴書は不要、服装自由、原則オンラインです。興味を持っていただけた方は、
ぜひ以下からお申し込みください。
皆さんにお会いできることをサクラグメンバー一同、心より楽しみにしております!
カジュアル面談応募フォームABOUT ME